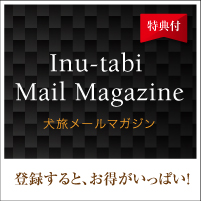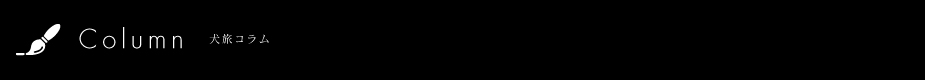

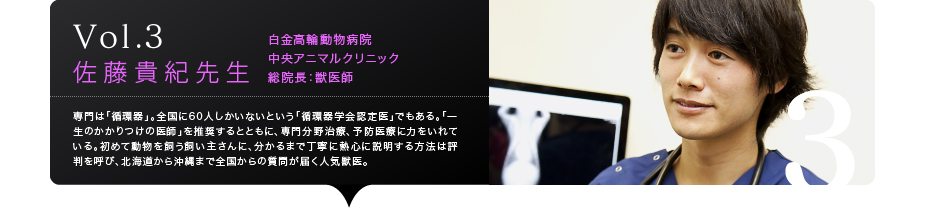
あなたは知っていますか?「嘔吐」と「吐出」の違いって何?
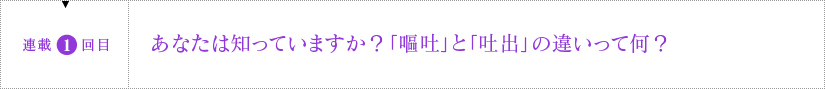
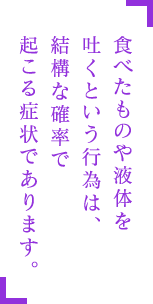
わんちゃんに一番多いお悩みは「吐く」という行為です。
わんちゃんが食べたものや液体を吐くという行為は、結構な確率で起こる症状であります。よって、何が原因なのかを見定める必要があります。
また、吐いた物が食前、食中、食後、食間のいつなのか、そして何を吐いたのかという情報は診断の助けになることは間違いありません。
そこで今回は嘔吐と吐出の違いをふまえて、今回はお話いたします。
まず、嘔吐は胃の内容物を吐いてしまう事。吐出は胃に入らず、口や食道にある物を吐き出す事。
消化されたフードを吐いた場合は嘔吐と言えますが、液体や未消化のフードを吐き出している場合は嘔吐か吐出かの判断はできないと言う事になります。
ただ、吐出の場合は空腹感が残りますので吐いた物をすぐに食べようとしますが、嘔吐の場合は気持ち悪いため基本的には再度ご飯を食べようとしないという傾向は見られます。
両方の原因としては…
嘔吐の原因は胃酸過多、内臓疾患や下痢、中毒、異物などさまざまです。
吐出の原因は食道炎、食道憩室などの食道の問題から、甲状腺機能低下症、重症筋無力症などこちらも様々です。
どちらも放っておくと重症化し、命の危険もありえます。
原因を定かにし、早期治療を心がけましょう。
わんちゃんが食べたものや液体を吐くという行為は、結構な確率で起こる症状であります。よって、何が原因なのかを見定める必要があります。
また、吐いた物が食前、食中、食後、食間のいつなのか、そして何を吐いたのかという情報は診断の助けになることは間違いありません。
そこで今回は嘔吐と吐出の違いをふまえて、今回はお話いたします。
まず、嘔吐は胃の内容物を吐いてしまう事。吐出は胃に入らず、口や食道にある物を吐き出す事。
消化されたフードを吐いた場合は嘔吐と言えますが、液体や未消化のフードを吐き出している場合は嘔吐か吐出かの判断はできないと言う事になります。
ただ、吐出の場合は空腹感が残りますので吐いた物をすぐに食べようとしますが、嘔吐の場合は気持ち悪いため基本的には再度ご飯を食べようとしないという傾向は見られます。
両方の原因としては…
嘔吐の原因は胃酸過多、内臓疾患や下痢、中毒、異物などさまざまです。
吐出の原因は食道炎、食道憩室などの食道の問題から、甲状腺機能低下症、重症筋無力症などこちらも様々です。
どちらも放っておくと重症化し、命の危険もありえます。
原因を定かにし、早期治療を心がけましょう。
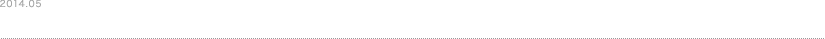
年に一度の混合ワクチンの必要性について…
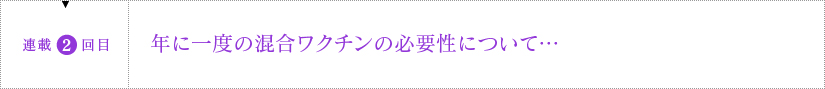
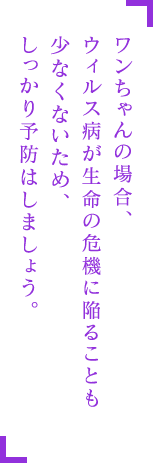
よく「混合ワクチンは本当に必要なんですか?」と聞かれます。
狂犬病のお薬は、義務化されていますが、ワクチンは義務化されていないですからよけいに皆さん、迷われているみたいですね。
「混合ワクチンをなぜ打つのか?」
皆さん御存じがない方が、多くいらっしゃるとは思います。
このワクチンは伝染病の予防、いわゆるウィルスによる伝染病の予防なのです。種類によっては細菌の予防にもなります。人間でもインフルエンザの予防注射を打つとは思いますが、その予防と同じ感覚ではあるのですが、ワンちゃんの場合、そのウィルス病が生命の危機に陥ることも少なくないため、しっかり予防はしましょう。
ワクチンの打つ時期としては「子犬」「成犬」によって違います。
子犬の場合 生後2ヵ月齢に一度、3か月齢に一度の計2回(最低でも)しかし、親からの免疫をしっかりもらっている場合などによっても違い、個体差はあります。
成犬の場合 一年に一回。日本では、この方法が一番多く取られています。
予防注射はあくまでもウィルス・細菌に対し、抵抗力をつける注射です。
ワクチンの種類には、たくさんあり5~9種類までのウィルス・細菌の病気を予防できます。
どの種類のワクチンをした方がいいのかは、獣医師にきちんとご相談していただければと
思います。
ワクチンは、年に一度の接種によって、病気を予防できるため、しっかりと接種するべきだと思います。飼い主さんによっては、『他の犬と接触しないし』とか、『外に出ないし』という飼い主さんがいますが、人間が外との出入りをするのであれば、感染する可能性は大いにあるため、気つけて下さいね。
とは言え、お薬ですから、ワクチンにもワクチンアレルギーなどの副作用も出てくる子もいます。必ず、専属の獣医さんにしっかり、お話を聞いた上、接種して下さい。
狂犬病のお薬は、義務化されていますが、ワクチンは義務化されていないですからよけいに皆さん、迷われているみたいですね。
「混合ワクチンをなぜ打つのか?」
皆さん御存じがない方が、多くいらっしゃるとは思います。
このワクチンは伝染病の予防、いわゆるウィルスによる伝染病の予防なのです。種類によっては細菌の予防にもなります。人間でもインフルエンザの予防注射を打つとは思いますが、その予防と同じ感覚ではあるのですが、ワンちゃんの場合、そのウィルス病が生命の危機に陥ることも少なくないため、しっかり予防はしましょう。
ワクチンの打つ時期としては「子犬」「成犬」によって違います。
子犬の場合 生後2ヵ月齢に一度、3か月齢に一度の計2回(最低でも)しかし、親からの免疫をしっかりもらっている場合などによっても違い、個体差はあります。
成犬の場合 一年に一回。日本では、この方法が一番多く取られています。
予防注射はあくまでもウィルス・細菌に対し、抵抗力をつける注射です。
ワクチンの種類には、たくさんあり5~9種類までのウィルス・細菌の病気を予防できます。
どの種類のワクチンをした方がいいのかは、獣医師にきちんとご相談していただければと
思います。
ワクチンは、年に一度の接種によって、病気を予防できるため、しっかりと接種するべきだと思います。飼い主さんによっては、『他の犬と接触しないし』とか、『外に出ないし』という飼い主さんがいますが、人間が外との出入りをするのであれば、感染する可能性は大いにあるため、気つけて下さいね。
とは言え、お薬ですから、ワクチンにもワクチンアレルギーなどの副作用も出てくる子もいます。必ず、専属の獣医さんにしっかり、お話を聞いた上、接種して下さい。
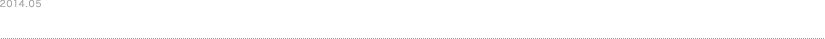
ミネラルウォーターは犬や猫にはあげてはいけないの?
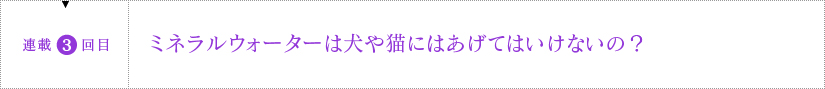
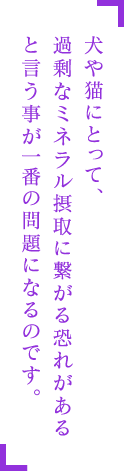
この質問は、よく聞かれる質問です。
特にこれからの季節「夏」に飲ませてしまう事が、あると思います。
しかし、絶対あげてはいけないと言う訳ではありません。
ただ、あまり頻繁に飲ませて欲しくないと言うのも事実です。
まず、ミネラルウォーターには硬水と軟水に分けられるのはご存知の通りかと思います。
このある一定基準のミネラル数を超えると硬水、それ以下を軟水と言うそうです。
いわゆるミネラルが豊富な方が硬水と言う事になります。
そんなにミネラルが豊富なら、良さそうなイメージがあります。
しかし、犬や猫にとって、過剰なミネラル摂取に繋がる恐れがあると言う事が一番の問題になるのです。
普段、総合栄養食を摂取している場合は、必ずしも他のミネラルは必要ありません。
食事でも、そして水からもミネラルを摂取することになります。
過剰摂取をするとどうなるかというと…
膀胱結石や腎結石などに繋がる恐れがあります。
この結石はカルシウムやマグネシウムなどのミネラルから主に構成されるため、注意が必要です。
過剰摂取はもちろん良くありませんが、水分量が不足している方が結石のリスクはあがるので、もしあげる場合は水道水もしくは軟水を選んでください。
一日摂取水分量は個体差もありますが、体重×50mlを目安に摂取することが理想です。もし、摂取できていないようであれば水分量をしっかり確保してください。
特にこれからの季節「夏」に飲ませてしまう事が、あると思います。
しかし、絶対あげてはいけないと言う訳ではありません。
ただ、あまり頻繁に飲ませて欲しくないと言うのも事実です。
まず、ミネラルウォーターには硬水と軟水に分けられるのはご存知の通りかと思います。
このある一定基準のミネラル数を超えると硬水、それ以下を軟水と言うそうです。
いわゆるミネラルが豊富な方が硬水と言う事になります。
そんなにミネラルが豊富なら、良さそうなイメージがあります。
しかし、犬や猫にとって、過剰なミネラル摂取に繋がる恐れがあると言う事が一番の問題になるのです。
普段、総合栄養食を摂取している場合は、必ずしも他のミネラルは必要ありません。
食事でも、そして水からもミネラルを摂取することになります。
過剰摂取をするとどうなるかというと…
膀胱結石や腎結石などに繋がる恐れがあります。
この結石はカルシウムやマグネシウムなどのミネラルから主に構成されるため、注意が必要です。
過剰摂取はもちろん良くありませんが、水分量が不足している方が結石のリスクはあがるので、もしあげる場合は水道水もしくは軟水を選んでください。
一日摂取水分量は個体差もありますが、体重×50mlを目安に摂取することが理想です。もし、摂取できていないようであれば水分量をしっかり確保してください。
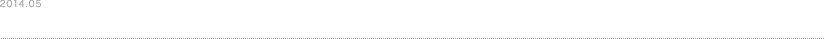
キャバリアは「心臓病」に要注意!
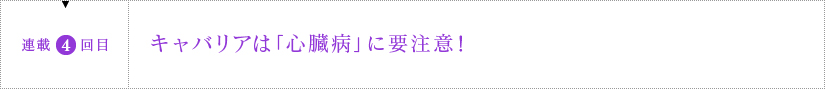
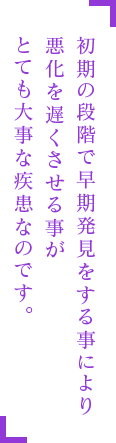
先日、キャバリアの飼い主さんから「心臓病に必ずなるのですか?」と聞かれました。必ずなる訳ではありません。なりやすい事は事実です。
キャバリアという犬種には、遺伝性の「心臓弁膜疾患」が多く見られます。
つまり「心臓疾患」です。
そもそもが、心臓疾患(心疾患)は、犬に多い病気の1つです。
心臓疾患と言っても、心筋が異常な心筋症や、弁が異常な弁膜疾患、また他に先天的奇形の中に通路が狭い狭窄疾患、異常な血管が存在する短絡疾患と大きく4つに別れます。
その中でキャバリア含め、小型犬にとって弁膜疾患は珍しくない病気です。
心臓疾患は悪化を防いだり、進行を遅くしたりすることが現時点では主な治療法ですが、最近では完治することは難しいものの、弁膜疾患を外科的に改善させ負荷を取り除く手術も行われるようになってきました。
大事な事は、初期の段階で早期発見をする事により悪化を遅くさせる事がとても大事な疾患なのです。
そんな、心臓疾患(心疾患)の中で、キャバリアがなりやすい弁膜疾患は病名「僧帽弁閉鎖不全」といいます。この病気は、心臓の中で血液を逆流しないように機能している弁「僧帽弁」の閉まりが悪くなる病気です。年齢では早い子は生まれた時から持っている事もあります。
この病気には、病状の段階があります。
キャバリアの場合には「心臓病」となる場合が多いと頭の中に入れて頂いた上で、少しでもおかしいと思いましたら、病院に連れていってあげて下さい。
キャバリアという犬種には、遺伝性の「心臓弁膜疾患」が多く見られます。
つまり「心臓疾患」です。
そもそもが、心臓疾患(心疾患)は、犬に多い病気の1つです。
心臓疾患と言っても、心筋が異常な心筋症や、弁が異常な弁膜疾患、また他に先天的奇形の中に通路が狭い狭窄疾患、異常な血管が存在する短絡疾患と大きく4つに別れます。
その中でキャバリア含め、小型犬にとって弁膜疾患は珍しくない病気です。
心臓疾患は悪化を防いだり、進行を遅くしたりすることが現時点では主な治療法ですが、最近では完治することは難しいものの、弁膜疾患を外科的に改善させ負荷を取り除く手術も行われるようになってきました。
大事な事は、初期の段階で早期発見をする事により悪化を遅くさせる事がとても大事な疾患なのです。
そんな、心臓疾患(心疾患)の中で、キャバリアがなりやすい弁膜疾患は病名「僧帽弁閉鎖不全」といいます。この病気は、心臓の中で血液を逆流しないように機能している弁「僧帽弁」の閉まりが悪くなる病気です。年齢では早い子は生まれた時から持っている事もあります。
この病気には、病状の段階があります。
| レベル1: | 特に症状もなく運動にも影響はありません。 |
| しかし、聴診をして心臓に雑音がある。 | |
| この場合、心臓が肥大している訳ではなく、超音波検査で心臓の中の血液が逆流しているのみの場合が多い。 | |
| レベル2: | 聴診で雑音があり、超音波検査やレントゲン検査で心臓が肥大している。 |
| 安静時は咳などの症状は無いが、興奮や運動後に咳などの症状がある。 | |
| この場合は、投薬が必要になります。 | |
| レベル3: | レベル2までの症状、検査所見があり、さらに安静時でも咳などの症状、また運動をしたがらないなどの症状が重なる場合。 |
| 身体的・精神的に常にわんちぁんに負担がかかってきています。 | |
| 他に、食欲が減る、体重が落ちる 、お腹が膨らんでいる、軽い運動をしても咳をする、舌が紫色になると言う病状が見えてきます。 | |
| 薬や食事療法を用いてしっかりと治療する必要があります。 | |
| レベル4: | 呼吸も苦しそうな状態になります。 |
| 常に舌の色も紫色となり、心臓の雑音も大きくなります。 | |
| いつ状態が急変してもおかしくない状態です。生命の危険も出てきます。この場合は入院が必要になります。 |
キャバリアの場合には「心臓病」となる場合が多いと頭の中に入れて頂いた上で、少しでもおかしいと思いましたら、病院に連れていってあげて下さい。
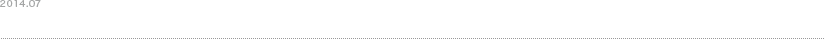
この季節ご用心!ちょっとした虫さされのような赤みが皮膚癌の恐れも!

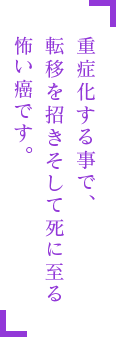
最近では、トリミングや家でのブラッシングが増えた事により、愛犬の皮膚にできたデキモノが小さい段階で気づく事ができるようになってきました。
しかし、気づいたとは言え、小さい事や痛がる事もないため様子を見ている患者さんが多いように感じています。
それでは、皮膚にできた赤みとはどのような物があるのか記述したいと思います。
・マダニやノミなどの外部寄生虫にさされた事による腫れ
・良性腫瘍含め、老齢的にできるイボ
・皮膚をぶつけてしまった時の外傷でできる血腫もしくは紫斑など
・見た目では判断が付きにくい、悪性の腫瘍(主に肥満細胞腫)
このような疾患があります。
そして、実は愛犬のまりもにも肥満細胞腫いわゆる皮膚癌ができ、手術を行う事となりました。
早い段階で手術を行うことができたので、外科的切除だけでしたが、病理検査によっては根っこが残り、再手術や抗がん治療、放射線治療などを行わなければいけないケースもあります。
そうならないためにも、早い段階で見つけたデキモノは一日でも早く、細胞診検査を行い悪性含め診断を付けた方が良いでしょう。
重症化する事で、転移を招きそして死に至る怖い癌です。
みなさんも気をつけましょう。
しかし、気づいたとは言え、小さい事や痛がる事もないため様子を見ている患者さんが多いように感じています。
それでは、皮膚にできた赤みとはどのような物があるのか記述したいと思います。
・マダニやノミなどの外部寄生虫にさされた事による腫れ
・良性腫瘍含め、老齢的にできるイボ
・皮膚をぶつけてしまった時の外傷でできる血腫もしくは紫斑など
・見た目では判断が付きにくい、悪性の腫瘍(主に肥満細胞腫)
このような疾患があります。
そして、実は愛犬のまりもにも肥満細胞腫いわゆる皮膚癌ができ、手術を行う事となりました。
早い段階で手術を行うことができたので、外科的切除だけでしたが、病理検査によっては根っこが残り、再手術や抗がん治療、放射線治療などを行わなければいけないケースもあります。
そうならないためにも、早い段階で見つけたデキモノは一日でも早く、細胞診検査を行い悪性含め診断を付けた方が良いでしょう。
重症化する事で、転移を招きそして死に至る怖い癌です。
みなさんも気をつけましょう。
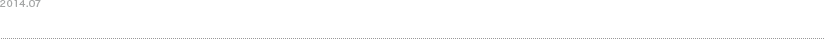
あなたの愛犬は大丈夫ですか?「ダニ媒介の新感染症」のお話
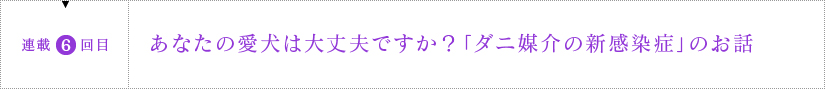
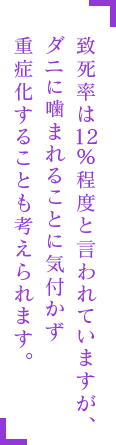
今週は、先月に報道されたマダニが媒介し人間にうつると言う、新しく、そして恐ろしい感染症のお話しをしたいと思います。
「重症熱性血小板減少症候群」(SFTS)と言われ、犬や猫に寄生するフタトゲチマダニがウィルスを媒介し、人間に感染することによって発熱、嘔吐、血小板減少などがあり死亡に至るとても怖い感染症です。
致死率は12%程度と言われていますが、ダニに噛まれることに気付かず重症化することも考えられます。
そして、現在では有効な治療法やワクチンは存在しないということです。厚生労働省によると、山野に入る際は長袖などを着てダニに噛まれない事が重要とのことです。
ここで考えられることは、愛犬もしくは愛猫に寄生したマダニによって飼い主さんが感染する可能性は大いに考えられるということです。
このフタトゲチマダニは全国的に見られており、今後感染が広がる可能性もあるわけです。
では、できる限りの予防としてはやはり愛犬、愛猫にマダニを付けさせない事が一番大切になる訳です。
うちの子は大丈夫という考えが自分の命をも脅かすことになる訳なので、しっかりとマダニ予防をすることをお勧めします。
マダニの予防法には飲み薬や付け薬など様々あるので、かかりつけの動物病院で相談してください。
1つだけ注意していただきたいのですがこの話しをすると「わんちゃんといるのが危険だから、飼わないほうがいいの?」と聞かれる方がいます。
決して、そうではありません。
飼い主さんが知識をもって、ケアをすれば未然に防ぐ事ができます。
わんちゃんと安心して暮らせます。
小さな家族を守る為にも「感染症の予防」はして頂きたいと思います。
「重症熱性血小板減少症候群」(SFTS)と言われ、犬や猫に寄生するフタトゲチマダニがウィルスを媒介し、人間に感染することによって発熱、嘔吐、血小板減少などがあり死亡に至るとても怖い感染症です。
致死率は12%程度と言われていますが、ダニに噛まれることに気付かず重症化することも考えられます。
そして、現在では有効な治療法やワクチンは存在しないということです。厚生労働省によると、山野に入る際は長袖などを着てダニに噛まれない事が重要とのことです。
ここで考えられることは、愛犬もしくは愛猫に寄生したマダニによって飼い主さんが感染する可能性は大いに考えられるということです。
このフタトゲチマダニは全国的に見られており、今後感染が広がる可能性もあるわけです。
では、できる限りの予防としてはやはり愛犬、愛猫にマダニを付けさせない事が一番大切になる訳です。
うちの子は大丈夫という考えが自分の命をも脅かすことになる訳なので、しっかりとマダニ予防をすることをお勧めします。
マダニの予防法には飲み薬や付け薬など様々あるので、かかりつけの動物病院で相談してください。
1つだけ注意していただきたいのですがこの話しをすると「わんちゃんといるのが危険だから、飼わないほうがいいの?」と聞かれる方がいます。
決して、そうではありません。
飼い主さんが知識をもって、ケアをすれば未然に防ぐ事ができます。
わんちゃんと安心して暮らせます。
小さな家族を守る為にも「感染症の予防」はして頂きたいと思います。
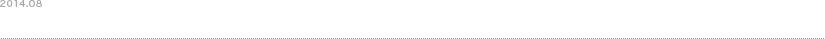
みんなで楽しく遊ぶ為に…「ドックランでの注意点と守って欲しい事」について…
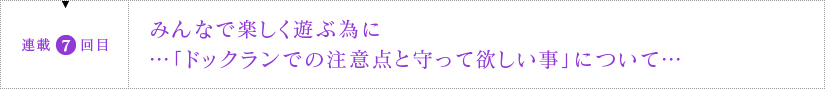
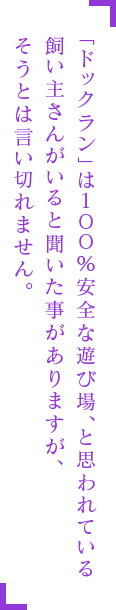
ワンちゃんと一緒に出掛けられる場所の中で、ワンちゃんが大好きな場所と言えばやはり「ドックラン」だと思います。
「ドックラン」は、リードを付けずに走り回れる唯一の場所ですよね。
そして、ワンちゃん同士が一緒に遊べる場所でもあります。
でも「ドックラン」でのトラブルが多いのも事実です。
そこで今回は「ドックラン」に入るためのマナーとして、注意点と守って欲しい事を獣医の立場からお伝えしていきたいと思います。
まずは「予防」をしているかどうかです。
地域によって少し違いはあるものの、混合ワクチンと狂犬病ワクチンの接種は欠かせないものになっています。
ただ、ワンちゃん同士が接触する中で、予防注射だけでは一部の予防しかできていないことになります。
例えば、ノミダニの予防やペットの糞からうつる消化管内寄生虫など、予防しておけば感染しにくい疾患もある訳です。
うつる感染症の中には命をおびやかす疾患も含まれるため、一緒にお出かけする人はできる限りの予防はした方が良いと思います。
また、犬同士が遊んでいるとはいえ咬傷事故などが起こる可能性もあり、ドックランから帰ってきたら、どこからか出血しているなんてケースもあるため、念のため、家に帰った際は、愛犬のコミュニケーションを取る意味合いでも全身を触ってあげてください。
また、手足の先なども良く見ると怪我をしているケースなどもあるため、気を付けてみてあげてください。
「ドックラン」は100%安全な遊び場、と思われている飼い主さんがいると聞いた事がありますが、そうとは言い切れません。
飼い主さんが十分に注意して、楽しく遊ばせてあげて欲しいと思います。
「ドックラン」は、リードを付けずに走り回れる唯一の場所ですよね。
そして、ワンちゃん同士が一緒に遊べる場所でもあります。
でも「ドックラン」でのトラブルが多いのも事実です。
そこで今回は「ドックラン」に入るためのマナーとして、注意点と守って欲しい事を獣医の立場からお伝えしていきたいと思います。
まずは「予防」をしているかどうかです。
地域によって少し違いはあるものの、混合ワクチンと狂犬病ワクチンの接種は欠かせないものになっています。
ただ、ワンちゃん同士が接触する中で、予防注射だけでは一部の予防しかできていないことになります。
例えば、ノミダニの予防やペットの糞からうつる消化管内寄生虫など、予防しておけば感染しにくい疾患もある訳です。
うつる感染症の中には命をおびやかす疾患も含まれるため、一緒にお出かけする人はできる限りの予防はした方が良いと思います。
また、犬同士が遊んでいるとはいえ咬傷事故などが起こる可能性もあり、ドックランから帰ってきたら、どこからか出血しているなんてケースもあるため、念のため、家に帰った際は、愛犬のコミュニケーションを取る意味合いでも全身を触ってあげてください。
また、手足の先なども良く見ると怪我をしているケースなどもあるため、気を付けてみてあげてください。
「ドックラン」は100%安全な遊び場、と思われている飼い主さんがいると聞いた事がありますが、そうとは言い切れません。
飼い主さんが十分に注意して、楽しく遊ばせてあげて欲しいと思います。
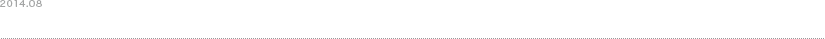
ペットだってあるんです!「花粉症」は平気ですか?
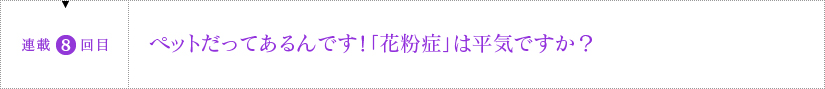
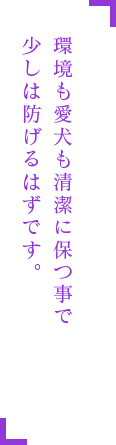
この時期になると、人間界では花粉症に悩まされる時期だと思います。
動物には花粉症はないと思っている飼い主さんもいらっしゃると思います。
しかし、そんなことはなく、もちろん犬や猫にも花粉症はあります。
ただ、アレルギー検査などを実際に行う事が少ないため、確定診断に至らないケースが多いのも事実です。これを「アレルギー性鼻炎」や「アレルギー性結膜炎」と呼んでいます。
わたくしも、花粉症であり、この時期は辛い思いをしています。これも、アレルギー検査をしたのでわかったことです。この季節に毎年、愛犬がくしゃみ、鼻水、結膜炎、皮膚のかゆみなどの症状を認める場合は、花粉症の疑いがあります。
当院においても、この時期に皮膚をかゆがり、くしゃみが止まらないというワンちゃんがいます。症状に応じてではありますが、重度であればステロイドが必要になり、軽度であれば抗ヒスタミン製剤を使用する、いわば人間と同じ治療になる訳です。
ただ、大きく違うのは人間のように予防ができないことです。マスクをしたり、眼鏡をかけたりなど花粉を近づけないことが大前提の花粉症において、犬の場合はどうすることもできません。
ただ、室内では空気清浄機を使用したり、散歩から帰ったらブラッシングをするなど、環境も愛犬も清潔に保つ事で少しは防げるはずです。
少しでも予防できるように、飼い主さんが気をつけてあげてください。
動物には花粉症はないと思っている飼い主さんもいらっしゃると思います。
しかし、そんなことはなく、もちろん犬や猫にも花粉症はあります。
ただ、アレルギー検査などを実際に行う事が少ないため、確定診断に至らないケースが多いのも事実です。これを「アレルギー性鼻炎」や「アレルギー性結膜炎」と呼んでいます。
わたくしも、花粉症であり、この時期は辛い思いをしています。これも、アレルギー検査をしたのでわかったことです。この季節に毎年、愛犬がくしゃみ、鼻水、結膜炎、皮膚のかゆみなどの症状を認める場合は、花粉症の疑いがあります。
当院においても、この時期に皮膚をかゆがり、くしゃみが止まらないというワンちゃんがいます。症状に応じてではありますが、重度であればステロイドが必要になり、軽度であれば抗ヒスタミン製剤を使用する、いわば人間と同じ治療になる訳です。
ただ、大きく違うのは人間のように予防ができないことです。マスクをしたり、眼鏡をかけたりなど花粉を近づけないことが大前提の花粉症において、犬の場合はどうすることもできません。
ただ、室内では空気清浄機を使用したり、散歩から帰ったらブラッシングをするなど、環境も愛犬も清潔に保つ事で少しは防げるはずです。
少しでも予防できるように、飼い主さんが気をつけてあげてください。
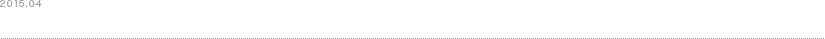
あなたは大丈夫?忘れがちなフィラリア予防薬の投与について・・・
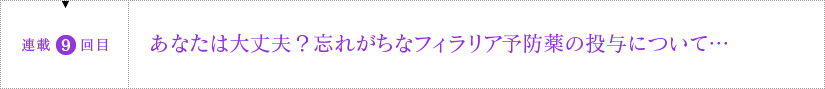
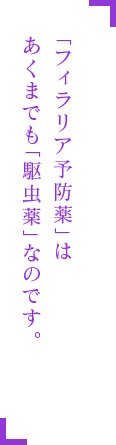
4月になると、必ずやっていただきたいのが「フィラリア」の予防です。
「予防」と言う言い方をするのですが、実は違います。「フィラリア予防薬」はあくまでも「駆虫薬」なのです。予防薬と言われているので、投薬後1ヵ月くらい効果があると勘違いしてしまうのですが、現段階で、動物病院で処方されている薬に関しては「駆虫薬」なのです。
つまり、万が一蚊に刺されていた場合に投薬をすることで、フィラリアの虫が大きくなる前に「駆除」しているという訳なんです。基本的にフィラリア予防薬は、蚊がいなくなった次の月が最終投薬月になるということです。もし、最後の月に投薬をしないと来春にはフィラリアが心臓に達している可能性もあるため、注意が必要です。
実は、まだまだフィラリア感染で亡くなっている犬は多く存在します。
気づかぬ間に心臓に大量寄生し、突然死を招いているケースや、咳や腹水など症状が重症化し苦しい思いをしている犬を見かけます。
これはあくまでも飼い主さんが予防を怠ることで起きてしまう病気です。ですので、予防をしっかり行い、正しい知識の元、大切な命を守りましょう。
「予防」と言う言い方をするのですが、実は違います。「フィラリア予防薬」はあくまでも「駆虫薬」なのです。予防薬と言われているので、投薬後1ヵ月くらい効果があると勘違いしてしまうのですが、現段階で、動物病院で処方されている薬に関しては「駆虫薬」なのです。
つまり、万が一蚊に刺されていた場合に投薬をすることで、フィラリアの虫が大きくなる前に「駆除」しているという訳なんです。基本的にフィラリア予防薬は、蚊がいなくなった次の月が最終投薬月になるということです。もし、最後の月に投薬をしないと来春にはフィラリアが心臓に達している可能性もあるため、注意が必要です。
実は、まだまだフィラリア感染で亡くなっている犬は多く存在します。
気づかぬ間に心臓に大量寄生し、突然死を招いているケースや、咳や腹水など症状が重症化し苦しい思いをしている犬を見かけます。
これはあくまでも飼い主さんが予防を怠ることで起きてしまう病気です。ですので、予防をしっかり行い、正しい知識の元、大切な命を守りましょう。